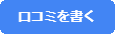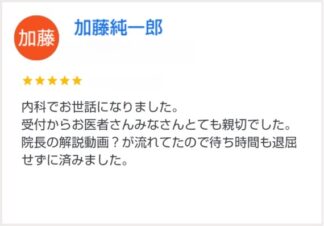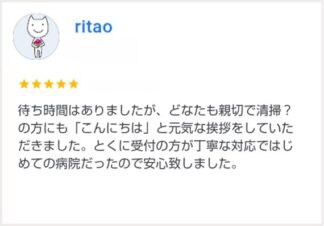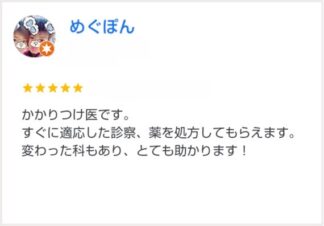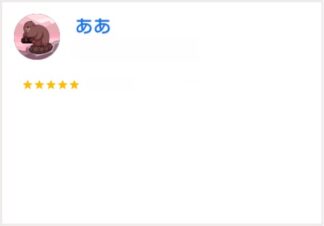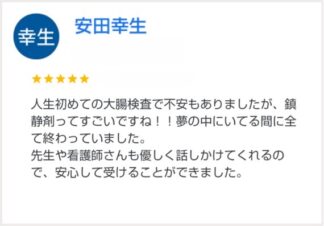先日、歌手のいしだあゆみさんが「甲状腺機能低下症」でお亡くなりになったというニュースが報じられ、甲状腺の病気について改めて関心が高まっています。
甲状腺に異常があると、体調不良の原因となるだけでなく、重大な病気につながる可能性もあります。
甲状腺の病気は、早期に発見し、適切に治療を行うことが非常に重要で、そのための有効な手段の一つが「甲状腺エコー検査」です。
今回のブログでは、「甲状腺エコー検査」とはどんな検査なのか、目的や方法、受ける目安となる症状などをわかりやすくご紹介します。また、検査結果の見方や血液検査との違いについても触れていきます。
甲状腺の異常は、自身では気づきにくいことも多いため、症状がない方でも定期的な検査が大切です。病院での検査に不安を感じている方や、何から始めればよいのか迷っている方も、まずはこの記事を通して、甲状腺エコー検査について知ることで、小さな気づきが将来の健康につながるかもしれません。
甲状腺って何?
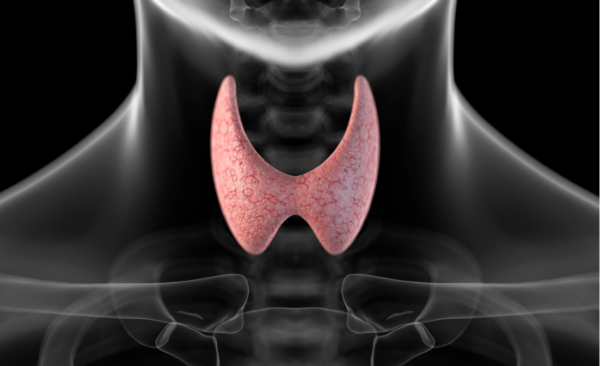 甲状腺は、首の前側、喉仏の下にある小さな臓器で、蝶のような形をしています。
甲状腺は、首の前側、喉仏の下にある小さな臓器で、蝶のような形をしています。
甲状腺ホルモンを分泌する役割を担っており、このホルモンは体の代謝を調節し、エネルギーの生成や体温の維持、心臓や脳の機能など、生命維持に不可欠な働きをしています。
甲状腺の異常とは
甲状腺の異常には、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。
- 甲状腺の形態異常:甲状腺が腫れたり、しこりができたりする状態です。
- 甲状腺機能の異常:甲状腺ホルモンの分泌量が多すぎたり(甲状腺機能亢進症)、少なすぎたり(甲状腺機能低下症)する状態です。
首の腫れだけじゃない、甲状腺の異常に伴う症状
甲状腺の病気は、首の腫れとして自覚されることが多いですが、それ以外にも様々な症状が現れることがあります。
例えば、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、心臓の働きが活発になって動悸や息切れが起こるほか、体温の上昇や発汗の増加、代謝の亢進によって食欲があるにもかかわらず体重が減少することがあります。
また、甲状腺ホルモンの分泌異常は、消化器系の機能に影響して便秘や下痢を引き起こすほか、精神面ではイライラや不安感、うつなどの症状を招き、さらに女性ホルモンのバランスを乱して月経不順を引き起こすこともあります。
さらに、甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、エネルギー代謝や体温、皮膚の代謝も低下し、倦怠感や疲労感、寒がり、皮膚の乾燥といった症状が現れることがあります。
これらの症状は、甲状腺ホルモンの分泌異常によって引き起こされることが多く、甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症といった病気が考えられます。
症状から考えられる甲状腺の病気
甲状腺の腫れや上記のような症状が見られる場合、以下の甲状腺の病気が考えられます。
- バセドウ病:甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、動悸、発汗、体重減少などの症状が現れます。
- 橋本病(慢性甲状腺炎):自己免疫疾患により甲状腺が炎症を起こし、甲状腺ホルモンの分泌が低下する病気です。倦怠感、寒がり、便秘などの症状が現れます。
- 甲状腺腫瘍:甲状腺にできる腫瘍で、良性のものと悪性のものがあります。腫瘍が大きくなると、首の腫れとして自覚されることがあります。
- 甲状腺炎:甲状腺に炎症が起こる病気で、亜急性甲状腺炎や無痛性甲状腺炎などがあります。
甲状腺がんによる腫れを良性腫瘍と勘違いし、放置して取り返しのつかない状態になるリスクもあります。
甲状腺エコー検査

甲状腺エコー検査は、甲状腺の形態的な異常を調べるのに有効な検査です。
甲状腺の病気を早期に発見し、適切な治療につなげるための重要な検査で、超音波を使って甲状腺の状態を詳しく調べる検査です。
体に負担の少ない検査で、放射線の被ばくもなく、痛みもほとんどないため、安心して受けられます。検査時間は5〜15分ほどで、リラックスした状態で受けていただけます。
何のために検査をするの?
甲状腺の大きさや形に異常がないか、しこり(結節)や腫瘍があるかどうか、炎症やのう胞といった異常がないかなどを確認するために行います。
検査によって、バセドウ病や橋本病、甲状腺腫瘍などの病気の早期発見・診断につながり、必要に応じて適切な治療へと進むことができます。
どんな場合に甲状腺エコー検査が必要?
以下のような場合には、甲状腺エコー検査を受けることをおすすめします。
- 首の腫れが気になる
- 甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症の症状がある
- 健診で甲状腺の異常を指摘された
- 家族に甲状腺の病気の人がいる
甲状腺の病気は自覚症状があまりないことも多く、健診や見た目の変化から偶然見つかるケースも少なくありません。最近では首の血管エコー検査の際に小さなしこりが見つかることも増えており、たとえ症状がなくても、首の腫れなど気になる変化があれば、早めに医療機関で甲状腺エコー検査を受けて原因を調べることが大切です。
甲状腺エコー検査で何がわかる?病気の種類と診断について
甲状腺エコー検査では、甲状腺の大きさや形の変化だけでなく、内部の構造や血流の状態まで詳しく観察することで、しこり(腫瘍)や嚢胞、炎症の有無などを総合的に確認することができます。
甲状腺エコー検査でわかる病気の種類
以下のような甲状腺の病気を発見することができます。
- 甲状腺腫瘍:甲状腺にできる「しこり」や「できもの」のことで、良性と悪性があります。
- 甲状腺炎:甲状腺に炎症が起こる病気で、慢性甲状腺炎(橋本病)や亜急性甲状腺炎などいくつかのタイプがあります
- 甲状腺嚢胞:液体の溜まった袋状の構造物
- 亜急性甲状腺炎:ウイルス感染などが原因で一時的に甲状腺に炎症が起こる病気
これらの炎症や異常が見つかった場合、血液検査で甲状腺ホルモン値や自己抗体を測定し、総合的に診断を行います。また、必要に応じて、経過観察や薬物療法などの治療を行います。
甲状腺腫瘍の診断:良性・悪性の判断基準
甲状腺エコー検査では、腫瘍の大きさや形状、内部構造、境界の明瞭さ、石灰化の有無などを観察し、良性か悪性かの判断に役立てます。
一般に、良性腫瘍は形が整っていて境界がはっきりし、内部が均一で血流も少ない傾向があります。一方、悪性腫瘍は形状が不整で境界が不明瞭、内部構造が不均一で血流が豊富なことが多いです。
| 特徴 | 良性腫瘍の可能性 | 悪性腫瘍の可能性 |
|---|---|---|
| 形状 | 円形または楕円形、境界明瞭 | 不整形、境界不明瞭、周囲組織への浸潤 |
| 内部構造 | 均一 | 不均一、嚢胞状の変化 |
| 石灰化 | 粗大石灰化、エッグシェル石灰化 | 微細石灰化 |
| 血流 | 少ない | 豊富 |
| リンパ節 | 所属リンパ節の腫脹なし | 所属リンパ節の腫脹あり |
ただし、これらはあくまで目安であり、確定診断には穿刺吸引細胞診(FNA)などの病理検査が必要です。また、エコー検査では良性に見えても、10mm以下の微小乳頭がんや微小浸潤型濾胞がん、髄様がん、悪性リンパ腫などは悪性の可能性があるため、血液検査や細胞診などを含めた総合的な判断が重要です。
検査結果の見方|甲状腺腫瘍の良性・悪性はどう判断する?
甲状腺エコー検査の結果を受け取った際、特に腫瘍が見つかると不安に感じる方も少なくありません。専門用語が多く戸惑うこともありますが、内容を正しく理解し、落ち着いて判断できるよう、検査結果の見方や用語の意味をわかりやすく解説します。
検査結果の用語を理解しよう
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 腫瘍(しゅよう) | 体内の組織にできる異常な塊。良性と悪性があります。 |
| 結節(けっせつ) | 甲状腺にできるしこりのこと。腫瘍と同様に、良性と悪性があります。 |
| 嚢胞(のうほう) | 体の中にできる“水ぶくれ”のようなもので、袋の中に液体がたまった状態を指します。甲状腺にできる嚢胞は、甲状腺嚢胞(こうじょうせんのうほう)と呼ばれます。 |
| 石灰化(せっかいか) | 組織にカルシウムが沈着すること。 |
| 低エコー | エコー検査で黒く表示される部分。甲状腺で低エコーが見つかると、良性のものや腫瘍、嚢胞などの可能性がありますが、悪性とは限らず、他の検査と合わせて判断されます。 |
| 高エコー | エコー検査で白く表示される部分。甲状腺で高エコーが見つかると、良性の石灰化や硬い部分などが考えられますが、悪性とは限らず、他の検査と合わせて判断されます。 |
再検査が必要な場合とは?
甲状腺エコー検査の結果、以下のような場合には、再検査や精密検査が必要となることがあります。
- 腫瘍のサイズが5mmを超える
- 悪性を疑う所見(微細石灰化、境界不明瞭など)が見られる
- 腫瘍が急速に増大している
- 頸部リンパ節の腫れが見られる
再検査では、超音波検査に加えてCTやMRIなどの画像検査、穿刺吸引細胞診などの病理検査が行われ、結果を総合的に判断して診断が確定されます。再検査が必要な場合は、医師の指示に従って適切な検査を受け、早期発見・早期治療を目指しましょう。
定期的な検査の重要性
甲状腺の病気は、自覚症状がない場合や、症状が軽微な場合でも、定期的な検査を受けることが非常に重要です。定期的な検査によって、病気の早期発見・早期治療が可能となり、重症化を防ぐことができます。
特に、甲状腺腫瘍が見つかった場合は、定期的なエコー検査で腫瘍の大きさや形状の変化を観察し、悪性化の兆候がないかを確認する必要があります。また、甲状腺機能異常の治療を受けている場合は、定期的な血液検査で甲状腺ホルモンの値を測定し、薬の量を調整する必要があります。
定期検査の間隔は、病気の種類や状態によって異なりますので、医師の指示に従ってください。また、体調に変化があった場合は、次回の検査を待たずに、早めに医師に相談しましょう。
また、家族に甲状腺の病歴がある方や、首の腫れ、声のかすれなどの症状がある方は、定期的な甲状腺エコー検査を積極的に受けることをおすすめします。
甲状腺エコー検査と血液検査
甲状腺の病気を正確に診断するためには、甲状腺エコー検査と血液検査の両方が重要です。それぞれの検査には異なる役割があり、組み合わせて行うことで、より精度の高い診断が可能となります。これにより、病気の特定や適切な治療方針の決定に役立てることができます。
それぞれの役割と違い
甲状腺エコー検査は、前述でも説明したように形態的な異常を発見するための検査ですが、これに対して血液検査は甲状腺ホルモン(FT3、FT4)や甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定し、甲状腺の機能的な異常を発見するための検査です。また、血液検査では自己免疫疾患に関わる抗体の有無も調べることができます。
血液検査でわかることの例
- 甲状腺機能亢進症:FT3、FT4が高く、TSHが低い場合に疑われます。
代表的な症状としては、動悸、息切れ、発汗、体重減少、イライラ、手指の震え、眼球突出(バセドウ病の場合)などがあります。 - 甲状腺機能低下症:FT3、FT4が低く、TSHが高い場合に疑われます。
代表的な症状としては、倦怠感、疲労感、寒がり、便秘、皮膚の乾燥、体重増加、むくみ、月経不順などがあります。 - 自己抗体の有無:バセドウ病や橋本病などに関連する自己抗体を調べます。
主な項目には、抗甲状腺レセプター抗体(TRAb)、抗サイログロブリン抗体(TgAb)、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)などがあります。
これらの異常は様々な症状を引き起こす可能性がありますが、他の疾患でも同様の症状が見られることがあるため、気になる症状がある場合は自己判断せず、医療機関を受診しましょう。
両方の検査を受けることの重要性
たとえば、エコーで腫瘍が見つかってもホルモン値が正常であれば良性の可能性が高く、逆にホルモン値に異常がある場合は、エコーに異常がなくても機能的な異常が疑われます。
このように、両方の検査結果を組み合わせて総合的に判断することで、病気の特定や適切な治療方針の決定に役立ちます。
【医師監修】甲状腺の不安を解消!検査後の適切な対応とは
検査結果に基づいた治療方針
甲状腺エコー検査の結果が出たら、医師が詳しく説明し、適切な治療方針を決定します。一般的には異常がなければ定期的な経過観察を行い、腫瘍や異常が見つかった場合は、さらに詳しい検査や治療が必要となることがあります。
治療方針は、病気の種類や進行度、年齢や健康状態などを考慮して決定されます。主な治療法には、薬物療法、手術、放射線療法などがあり、橋本病や甲状腺機能低下症の場合は、甲状腺ホルモンを補充する薬物療法が中心となります。バセドウ病や甲状腺機能亢進症の場合は、甲状腺ホルモンを抑える薬や、放射性ヨード治療、手術などが用いられます。
治療を始める際は、内容や副作用について医師の説明をよく聞き、納得した上で進めることが大切です。疑問や不安があるときは、遠慮せずに医師へ相談しましょう。
日常生活で気をつけること
甲状腺の病気と診断された場合、治療と並行して日常生活での注意も重要になります。
- 食事
一部の疾患については、ヨウ素の過剰摂取を避けることが推奨される場合があります。海藻類に多く含まれるヨウ素の摂取量について、医師の指示に従いましょう。 - ストレス
ストレスは甲状腺の病気を悪化させる可能性があります。規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠と適度な運動、趣味などでリラックスする時間を持つことが大切です。 - 喫煙
喫煙は特にバセドウ病の悪化リスクと関連があります。治療の一環として、禁煙を意識しましょう。 - 服薬
医師から処方された薬は、指示通りに服用し、自己判断で服薬を中断したり量を調整するのは避けましょう。また、甲状腺ホルモン薬は、食事の影響で吸収が変わることがあるため、服用のタイミングについては医師や薬剤師に確認しておくと安心です。
これらの注意点は、あくまで一般的なものです。個々の病状や治療内容によって、注意すべき点は異なる場合がありますので、必ず医師の指示に従ってください。
甲状腺の病気に関する相談窓口

甲状腺の病気について、不安や疑問がある場合は、専門の医療機関や相談窓口を利用することも有効です。
- 医療機関:内分泌内科、甲状腺外科など、甲状腺の専門医がいる医療機関を受診しましょう。
- 医療相談窓口:各都道府県や市区町村には、医療に関する相談窓口が設置されている場合があります。
- 患者会:同じ病気を持つ人たちが集まる患者会では、情報交換や交流を通じて、精神的なサポートを受けることができます。
これらの窓口を活用し、甲状腺の病気に関する正しい知識を身につけ、安心して治療に取り組めるようにしましょう。
まとめ|甲状腺エコー検査で早期発見・早期治療を!不安な場合は専門医へ相談を
甲状腺エコー検査は、甲状腺の異常を早期に発見するために非常に有効な方法です。自覚症状が出にくい甲状腺の病気も、定期的な検査を通じて早期発見が可能となり、適切な治療へ繋げることができます。首の異常を感じたり、甲状腺機能に不安がある場合は、専門医に相談し、検査を受けることが、健康維持において非常に重要です。
早期発見・早期治療のためにも、気になる症状があれば、自己判断せず、専門医に相談しましょう。
当院では、経験豊富な医師が丁寧に検査を行い、結果についても詳しく説明いたします。甲状腺に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。